御霊前や御香典という言葉を耳にしても、実際に使い分けようとすると迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
特にお通夜や葬儀の場では、正しい表書きの知識が求められます。
この記事では、御霊前とお香典の違いを明確にし、どちらをいつ、どのように使うべきかを詳しく解説します。
この記事を読むと以下のことがわかります:
- 御霊前と御香典の基本的な違い
- 宗教や時期による使い分け方
- 各表書きの書き方とマナー
- 香典の金額相場と渡し方
御霊前とお香典の違いとは?
お通夜 御霊前 御香典 どっちが正解?
結論から言うと、仏式のお通夜では「御霊前」が基本です。ただし、宗派や地域により使い方は異なります。
浄土真宗など一部の宗派では通夜から「御仏前」となるため、相手の宗派を確認することが大切です。
一方、「御香典」は宗派を問わず使える表書きのため、宗派が不明な場合や無宗教の儀式に参列する際に使われます。
香典袋を準備する際は、用途に応じて最適な表書きを選びましょう。
御香典と書くのはいつまで?
御香典は広義で使用される表現ですが、仏教では使うタイミングに注意が必要です。
忌中である四十九日までは「御霊前」、それ以降の法要では「御仏前」が基本です。
したがって、「御香典」と書いても大きなマナー違反ではありませんが、相手に配慮するならば時期と宗派に応じて書き分けるのが望ましいです。
ご香典 御霊前 の違いとは
「ご香典」は口語であり、正式な表書きには「御香典」と記載します。
「御霊前」は亡くなった直後、まだ仏となっていない故人に捧げる供物という意味を持ち、仏教の忌中に使われる言葉です。
違いを意識することで、適切な香典マナーを実践できます。
御香典とは何か?
「御香典」は、元来は香を供える意味を持ち、今では金銭を供える行為に使われます。
どの宗教でも基本的に失礼にあたらない表書きですが、キリスト教では「御花料」、神道では「御玉串料」など、より適した表書きがあります。
御霊前の正しい使い方とマナー
御霊前 書き方の基本
香典袋の中央上部に「御霊前」と毛筆や筆ペンで記載します。
忌中であれば薄墨を使用するのが伝統的なマナーです。
薄墨には「悲しみで墨が薄れた」という意味が込められています。
参列者の氏名は表書きの下に記載し、フルネームが基本です。
連名で記載する場合は3名まで、4名以上なら代表者の氏名と「外一同」などと書きましょう。
御霊前 金額の相場
香典に包む金額は以下が目安です:
| 関係性 | 金額の目安 |
|---|---|
| 両親 | 5〜10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3〜5万円 |
| 祖父母 | 1〜3万円 |
| 友人・知人 | 5千〜1万円 |
| 仕事関係 | 5千〜3万円 |
地域や慣習、個人の事情によっても異なるため、無理のない範囲で選びましょう。
御霊前 いつまで使うべき?
御霊前は四十九日を迎えるまでの忌中に用いる表書きです。
四十九日法要を過ぎると故人は成仏し、「御仏前」に表記を切り替えます。
また、キリスト教や神道の葬儀では「御霊前」を使わず、それぞれに適した表書きが存在します。
以下に宗教ごとの表書きをまとめます。
| 宗教 | 表書き |
|---|---|
| 仏教 | 御霊前(忌中)/御仏前(忌明け) |
| 神道 | 御玉串料、御神前 |
| キリスト教 | 御花料(プロテスタント)/御霊前(カトリック) |
| 無宗教 | 御香典、御供物料 |
御香典 書き方の違い
表書きには「御香典」と記載し、中央に大きく記します。使用する文字は黒墨ですが、突然の訃報時は薄墨でも構いません。中袋がある場合は金額と氏名・住所を記載し、漢数字は旧字体を用います。
| 一 | 壱 | | 二 | 弐 | | 三 | 参 | | 五 | 伍 | | 千 | 仟/阡 | | 万 | 萬 | | 円 | 圓 |
例えば「金五千円也」は「金伍阡圓也」と書きます。
宗派別の表書きマナーと使い分け
浄土真宗では御霊前は使わない
浄土真宗では、人が亡くなるとすぐに成仏する教えがあるため、通夜・葬儀ともに「御仏前」を用います。
「御霊前」は不適切とされるため注意が必要です。
キリスト教では御花料
キリスト教のプロテスタントでは「御霊前」は使わず「御花料」とします。
カトリックでは「御霊前」も使われますが、迷ったら「御花料」が無難です。
神道では御玉串料が一般的
神道では「御霊前」も使えますが、「御玉串料」「御神前」の表書きが適切です。
五十日祭以降では「御神前」などに切り替えましょう。
香典袋とマナーのポイント
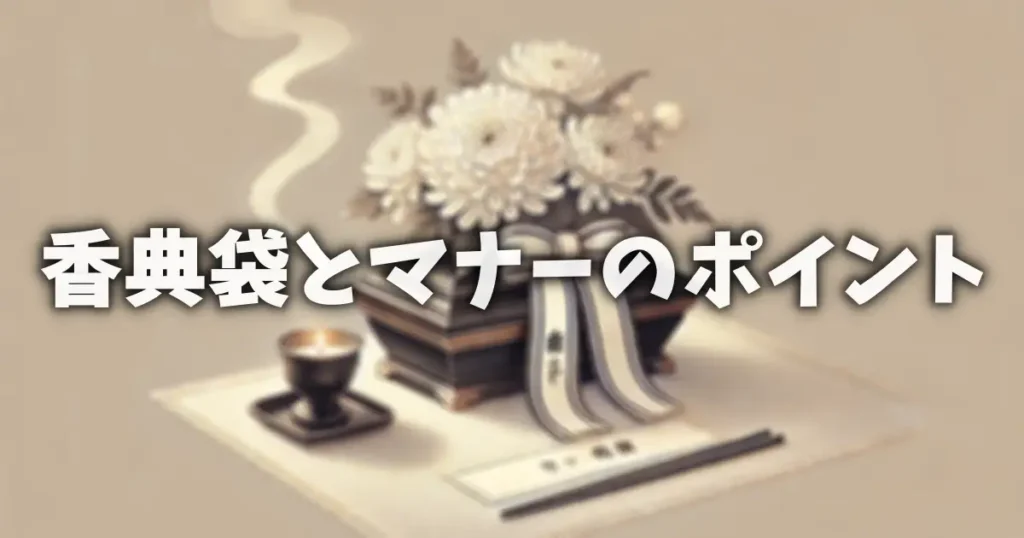
不祝儀袋の選び方
不祝儀袋は金額に応じて以下を参考にしましょう:
- 3千円以下:印刷タイプの簡易袋
- 5千円〜1万円:水引付きの袋(白黒または双銀)
- 3万円以上:中金封、豪華な水引付き
地域の風習によっても異なるため、事前確認が大切です。
お札の入れ方
香典には新札は避け、折り目をつけた旧札を使用します。肖像画が裏側になるようにし、封筒の底側に向けて入れます。
香典を渡すタイミングとマナー
香典を渡す場面
通夜または葬儀の受付で渡します。両日参列する場合、どちらか一方で渡せば問題ありません。
渡す際は一礼し、ひと言お悔やみの言葉を添えましょう。
例:「この度はご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます。」
袱紗(ふくさ)の使用方法
袱紗に包んで持参するのが礼儀です。落ち着いた色の無地が適しています。
香典を取り出す際は、袱紗を座布団のように使い、両手で丁寧に差し出します。
郵送する場合の注意点
やむを得ず参列できない場合、香典は現金書留で郵送します。
手紙を添えるのが丁寧で、句読点を避け、簡潔に気持ちを伝える文章が好まれます。
例文: 「このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
略儀ながら、御霊前にお供えくださいますようお願い申し上げます。」
よくある質問(Q&A)
Q:香典を連名で出す場合、名前はどう書く? A:3名までは連名で記載、4名以上なら代表者+「他一同」とし、別紙に全員の氏名・金額を添えます。
Q:香典辞退と案内されたらどうする? A:持参は控え、代わりに供花やお供物を送るのが一般的です。事前に喪主の意向を確認しましょう。
Q:学生は香典を出すべき? A:基本的には不要です。参列する場合も、家族と一緒にするか、連名で供花を贈る等で気持ちを伝えます。
まとめ:御霊前とお香典の違いを理解して正しいマナーを
- 御霊前は忌中(四十九日まで)に使用する
- 御香典は宗派を問わず使える表書き
- 表書きは毛筆か筆ペンを使い、薄墨は忌中限定
- 仏教では四十九日以降は「御仏前」に切り替える
- 宗教別に適切な表書きを選ぶ必要がある
- 金額は関係性に応じて包む
- お札は折り目を入れ旧札を使用する
- 中袋には金額・住所・氏名を記載
- 香典袋は金額や宗派で選び方が異なる
- 香典は袱紗に包み受付で渡すのがマナー
- 渡す際はお悔やみの言葉を添える
- 参列できない場合は現金書留と手紙を送る
- 表書きに迷ったら「御香典」が無難
- 浄土真宗では「御霊前」は使わない
- 団体で渡す場合は代表名義と別紙で記載
御霊前や御香典に関する知識は、いざという時に大切な配慮となります。
相手の宗教・時期・立場に合わせて、正しいマナーを心がけましょう。







コメント